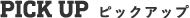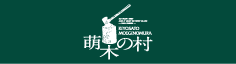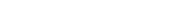12月9日、ROCKで1本の映画の上映会が行われました。2011年に公開された、山梨県甲府市を舞台にした映画『サウダーヂ』の上映会です。
監督は甲府市出身の富田克也さん。空族(くぞく)という映画制作集団のメンバーでもあります。そして、会場には同じく山梨県出身で、爆音映画祭の生みの親でもある評論家・樋口泰人さんも登場。『サウダーヂ』の脚本を担当した相澤虎之助さんと3人で、地方の疲弊、空洞化といった実態を描いた『サウダーヂ』について改めてトークを行ってくれました。
実は、萌木の村の野外ステージで何か映画祭のようなイベントを開催できないかという話しもしており、富田さん、樋口さんらが集まっていました。イベントの実現はまだ先になりそうですが、山梨県を出発点に、日本の地方都市を見つめてきた富田監督たちが、今何を考えているのか、この機会に三上が話を聞きました。
日本中のロードサイドがパチンコ屋とATM、牛丼屋になった時代
三上 昨日の上映会はありがとうございました。まずは『サウダーヂ』の話を聞きましょうか。そもそも『サウダーヂ』という作品を撮るきっかけは何だったんですか?

富田克也さん。
富田 この作品の前に『国道20号線』っていうタイトルの作品があるんです。ドンキにTSUTAYAがホットスポット、パチンコ屋の隣に消費者金融のATMが並んでて、パチンコ屋から出てきた人がATMに入っていき、またパチンコ屋に入って吸い取られ、残った小銭で吉野家へ……。そんな往復だけしている人々の姿が、地方都市の状況を象徴していると思って撮ったのが『国道20号線』なんです。
三上 それがいつの作品ですか?
富田 公開が2007年です。 あの頃は、自分たちの生まれ故郷である(山梨県の)甲府で、目の前にあるものをそのまま映したようなつもりだった。でも、公開したあとにいろんなことを自覚させられていったんです。全国のミニシアターで公開されて、トークショーなんかで足を運ぶでしょう? そうするといろんな地方都市を見ることになる。そのときに初めて「甲府だけじゃなくて、日本全国のロードサイドというのが全部同じ景色になってしまっている」と気付いたんです。パチンコ屋と消費者金融のATM、チェーン店ばかり。地方ごとの特色というのが、一見しただけではわからないくらいなくなってしまっていた。ちょうどそのころ、世の中でも「地方の空洞化」「疲弊」なんてことがいわれるようになってきて。じゃあ、それってどういうことなんだろうって思って撮ったのが『サウダーヂ』というわけです。
三上 その題材がすごいと思うんですよね。そこって、みんな嫌がるところ、目をそらしたいところじゃないですか。
富田 僕らはそもそも映画が好きで、いろんな映画も見てきた。同時に最近の商業映画ってほんとにおもしろくないと感じてもいた。だったら自分たちが撮ろう、と。そのなかで『国道20号線』や『サウダーヂ』みたいなテーマが見つかっていったんです。
三上 樋口さんが爆音映画祭を始めたのも同じ頃ですよね。

樋口泰人さん。
樋口 そうですね。第1回目の爆音映画祭が2004年。来年で15周年になります。富田くんとも爆音映画祭で知り合ったのかな? 『国道20号線』を爆音でやったんだよね。知り合いに勧められて見に行ったら面白くて。これを爆音でかけたいなって。
富田 俺も爆音映画祭という存在は知っていたけど、最初は全然理解できてなかったです。ただガーンとでかい音にしている酔狂な人たちって思ってた(笑)。だけど、知れば知るほど面白いんですよ。
樋口 『国道20号線』だと、バイクの音とかね。これ、こんな大きい音で入れるのかってくらい大きな音で入れてて(笑)。
富田 劇場全体がビリビリするくらい(笑)。『地獄の黙示録』の空爆シーン並の爆音になっちゃって。
樋口 普通ならそういうのって音量を抑えるんだけど、俺らは面白がって逆に上げちゃって(笑)。
富田 爆音映画祭ってそういうことなんです。こんなバイクの排気音に反応してくれるの?って(笑)。つまり、ただ音量を大きくしたり、綺麗な音に調整しているんじゃなくて、樋口さんの目や耳にはその映画がこう映っているんだっていうのを見せている。いってみれば爆音という形のリマスター、更に音側からの批評になっている。だから、爆音映画祭以降、似たような企画はたくさん出てきたけど、爆音映画祭は、樋口さんの耳のおかしさ、変態性みたいなものから生まれていて、理路整然としたものじゃないんです。それが面白い。
つまらない世の中をつついてやると少し変わる
樋口 爆音映画祭は吉祥寺のバウスシアターという劇場で生まれて、ずっとそこを拠点にやってきたんですが2014年にバウスシアターが閉館してしまった。それは大変なことだったんだけど、結果的にそこからいろんなところで爆音映画祭をやるようになっていったんです。日本はもちろん、ロシアでもやったり。そうなったときに、同じ作品、例えば『グレイテスト・ショーマン』とかを広島でやって、次は仙台でやると、全部の会場を見に来る人がいるんです。
富田 映画ってコピーに次ぐコピーなわけです。そのコピーがいろんな劇場に配られて、上映されていく。でも、厳密にいえば各劇場の大きさや設備によって音も色も違う。「ここはいいな」とか「ここは聞きづらいな」とかあるんです。だけど、普通の人は1回見たらその体験が「その映画」だと思って記憶する。爆音映画祭は「この場所、このスクリーンで見るとこんな特性があるんですよ」っていう、同じ映画で違いを際立たせているんです。映画はもちろんライブではないけど、ライブを見るのに近い感覚。

三上浩太。
三上 ヴァルター・ベンヤミンのいうアウラ(一回性の持つ神秘のようなもの。ベンヤミンは演劇や音楽の生演奏などにはアウラがあり、同じものの繰り返しになる映画などの芸術はアウラを喪失していると論じた)の話みたいですね。アウラを喪失しているはずの映画が、一種のアウラを獲得する方向に進んでいる。
樋口 そうですね。演劇から映画へ、という流れとは逆になっている。ただ、演劇のようなもの、時代に戻っているわけでもない。ライブそのものではないんですよね。失ったものとしてのアウラっていうのが、何か出ていて、それを面白いってみんなが思っている。で、面白がって会場を回ってくる人たちを見ているでしょう? だいたい男女半々、女性の方がちょっと多いくらいなんだけど、「どうやって暮らしてるの?」って聞くと「普通に働いてる」っていうんですね。それで話していくと、どうもみんな「普通に暮らしてるその暮らし自体は面白くない」って思ってる気がするんです。だからこそ、何か面白いものがあったらそこに行きます、と。そこに関してはお金も惜しまない。そういう楽しみのために働いているからって。何かね、「このつまらない世の中でずっとおとなしくしている気はありません」って気持ちを感じるんだよね。
富田 なるほど、そういう感じか。
三上 僕らの世代、平成生まれって超現実主義で、何かあっても「仕方ないよね」と諦めているところがある。だから、同級生たちを見ると、こういうものに興味がないのかぁと感じたりもするんです。一方で僕自身は富田さんや樋口さんの感覚に共感を感じたりする。
樋口 僕は、そういうふうに現実的に生きている人でさえ、ちょっとしたことで変わる感じになってるんじゃないかと思うんです。爆音映画祭を通じて、何かこっちがちょこっとうまいこと刺激すると人は動くんだなって実感した。
上映会という一回性とシネマツーリズム
富田 体験としての映画っていうのは、僕らもいわれることなんです。
三上 作品をソフト化しないですもんね。
富田 それもね、別に「しない」なんていったことはないんですけどね。もはや都市伝説的に「ソフト化しない」ということになってしまった(笑)。もともとは、映画というもののローテーションを変えたいっていうのが目的だったんです。つまり、映画を公開して3か月後にDVDやブルーレイでソフト化しちゃうのが今や当たり前になっている。だけど、そうしたらみんなソフトを待って映画館に来なくなるなんて当然のことじゃないですか。『国道20号線』をつくったのは、そういうローテーションを変えたいという話からでもあるんです。映画館もなくなっていく一方という状況で、映画をつくったとしても上映してくれる劇場はなかなかない。そこには映倫なんかも壁として立ちはだかる。そう考えたときに、僕らは場所をつくらないといけないって思ったんです。今までは場所というのは誰かがつくってくれていた。ゲームセンターでもイベントでも、大人たちが用意してくれて、俺たちはそこで遊ぶだけでよかった。でも、そういうものも画一化の流れのなかでどんどん多様性を失っていって、最終的に「イオンがあればいいだろう」ってなってしまったのが地方都市じゃないですか。そうなったときに、俺たちはどこで遊べばいいんだろうって。その場所を自分たちでつくっていかなきゃいけないだろうって話になったのが、『国道20号線』のときだったんです。会場なんかも自分たちの手弁当でやり始めて、チラシをつくって、甲府でイベントを始めて。

12月9日にROCKで行われた『サウダーヂ』上映会の様子。多くの関係者が登壇した。
三上 爆音映画祭にも近いものを感じますね。
富田 うん。ただ、地方でやることで気付いたこともあるんです。東京だと、この箱ならこういう客層、この箱ならこれくらいの年齢層っていうのがもうできあがっている。でも、地方でやると、ひとつの箱にあらゆる世代、あらゆるジャンルの人が集まって、ごちゃ混ぜになる。それを見ていて、面白いなって思い始めたんです。じゃあ、自分たちが勝手につくった映画で勝手に上映会やって、ソフト化は5年後とかにする。そういうローテーションで成立するようにすれば、映画館に来てくれるようになるだろうって。僕らは映画自体ももちろん好きだけど、映画館で同じスクリーンを見つめるっていうあの空間が好きだから。それがいつの間にか「ソフト化しない」って話になっちゃったんだけど。
三上 でも、結果的に着いてきてくれる人も生まれたわけですよね。
富田 昨日のROCKでの上映会でも、京都から来たって人がいたよ。
樋口 え? なんで?
富田 今大学で映画を専攻してて、移民問題とか、入管法改正とかを題材にして映画を撮ってるらしいんですよ。それに伴って卒論も書かないといけない。だから『サウダーヂ』は絶対に見ておかないとってことらしいんだけど、ずっとチャンスがなくて見られなかったんだって。この間金沢でも上映会あったんだけど、それも逃しちゃって、ここが最後のチャンスだったって。そういうのを聞くと「ああ、そんな苦労をかけてしまって…」と反省したりもするんだけど。でも、少し前の時代を思い返せば、すべてはそういうものだったよね?限られた情報しかなかったし、よっぽど能動的にアンテナを立てて、更に行動力も必要で、やっと何年もかかって辿りついたり手に入れたり。そういうのって、人生の宝物のように心に残っていますから。だから、いいよね?楽しんでくれてるよね?って自分に言い聞かせたりしてました。テアトル石和で「バンコクナイツ」を公開したときに、東北や広島、更には沖縄から来てくれた人たちもいて。訊けば、どうせ関東圏まで来るのなら、俺たちの地元に見に来た方がなんか面白いことが起こるんじゃないかと期待してくれていたりとか。たとえばBIG FLAT(山梨県を拠点に活動するヒップホップユニット・stillichimiyaのアンテナショップ)に寄って、ROCKでカレー食べたり、蓬莱軒でラーメン食べたりって、「サウダーヂ」や「国道20号線」のロケ地巡りしたりと自主的にコースを決めていろんなところを回ってくれる人がたくさんいる。それこそワインツーリズムみたいに。それってやっぱり嬉しいじゃないですか。それに、映画自体だって、同じ作品でも、観る場所や時期でも随分印象が変わる。昨日の「サウダーヂ」上映後も、7年前とでは全然違って見えた、今の方がグッとくるという感想が多かったです。やはり映画は体験なんです。爆音映画祭はそういうことを、音の側からさらに一工夫してやってるイベントですよね。
雑さの失われた時代
樋口 地方での上映会って面白いんだよね。
富田 昨日のROCKでの『サウダーヂ』上映会もよかった。音、すごくいいじゃん。
三上 もっと調整すれば爆音もできると思います。昨日は完璧な調整はしきれなかったんですけどスピーカーはメイヤーサウンドなんでそれこそ樋口さんに爆音用に調整していただければ。
富田 野外もいいけど、屋内で爆音映画祭やるのもいいと思うんだよね。これだけいい設備があるんだから。

萌木の村で爆音上映会をやるなら屋外ステージ? そんな相談も少しずつ進められている。
樋口 うん、地方だとさ、もっとすごいところで上映会やったりもするんですよ。暗幕もないようなところで。前にサミュエル・フラーを配給したときに、突然鹿児島の方から連絡が来たことがあるんです。鹿児島だと絶対にどこでもやらないから、自主上映だけどやりたいって。それで行ってみたら、主催は女の子たちで。だから、サミュエル・フラーなのにチラシがピンクだったり(笑)。
一堂 (笑)
樋口 で、場所もカフェの2階で、暗幕がないから暗くなったら上映という形。窓の外で走ってる車のヘッドライトなんかも見えたりするんだけどね。だけど、上映会をやるとサミュエル・フラーって名前で集まるような人たちももちろんいるんだけど、そういう感じじゃない女の子たちもたくさん来る。すごいなって。さっき東京だと箱でお客さんが決まってしまうって話があったけど、地方は東京よりも豊かな広がりを感じるんですよね。東京だったら、こういう上映会って潰されちゃったりするじゃん。「サミュエル・フラーをやるならもっとちゃんとしたところで!」とかさ。でも、そうじゃない、雑なところも絶対必要だと思うんだよね。
富田 雑だったよね、俺たちのガキのころって。学校サボって『ロッキー4』見たりしてたけど、しかも入れ替えがないから千円ちょっとで1日中館内にいられるって最高だった。それで『ロッキー4』を4回見て、もう完全に覚えちゃったりね。さらに当時は映画というのは必ず二本立てでさ、目的の映画ではないものも強制的に観ることになって、もしろそっちに衝撃受けたりしてたわけですよ。今は、そういう余白がない、ピンポイントの世の中ですよね。
思ったようにいかないという前提が生むおおらかさ
樋口 雑さって大事だよ。爆音映画祭でロシアに行ったときもさ、モスクワの中心みたいな街で一番の映画館でやったんだけど。それがさ、いろいろあって朝4時間とか待たされたの(笑)。映画館自体も映写室が低くてね、人が通るとライトにかぶるようなつくりで、しかも内装工事中で壁を塗りながらオープンしてるの(笑)。日本でいったら渋谷とか原宿みたいなところの一番大きな映画館だよ?
富田 さすがですね(笑)。

樋口 で、それだけならまだしも、エンドロールが流れはじめると人が出て行き始めるでしょ? そうするとライトにかぶるわけ。そうしたら、見に来てた子どもが面白がって影絵とか始めるんだよ(笑)。制作者はショックだろうけど、映画を見るという子どもの体験としてはものすごく面白いだろうって。そういうのってもう日本では考えられなくなっちゃってる。
富田 ロシアって寒いから神経質なイメージあるけど、そういうわけでもないんですね。
樋口 ピリピリしてる人もいると思うよ。でも、ロシアってさ、多民族国家なんだよ。だから、いろんな人がいる。4時間待たされたときも、担当者はさすがに自分の責任だからすごい謝ってきたりするんだけど、こっちは「まあまあ」って(笑)。そうやっていろんな人がいるから誰も自分のペースで、思ったようにはいかないっていうのが当たり前のようになっている。それがすごく面白かった。だから、日本ももっといろんな人が来てぐちゃぐちゃになるとそうなっていくのかもね。
三上 思ったようにいかないという前提は大切なんでしょうね。日本はそれがない。
樋口 爆音映画祭もまさにそれで、でかい音にしたらまったくコントロールできないわけです。思ったようにいかないところの面白さをどう拾い上げるかという話なんです。
富田 いいこと言うな~。最近、ネットでの炎上騒ぎなんかをみてると……
樋口 もう一切失敗できない感じだよね。みんな間違いなんてするわけじゃん。それを思いっきり攻撃されるんだから、たまんないよ。
富田 樋口さんの4時間待たされた話じゃないけど、俺たちの後輩の木村文洋って映画監督がね、エジプトの映画祭に呼ばれて現地に行ったんだけど、空港に着いても迎えがいない。でも、初めてだし、ひとりだし、電話もできないし、どうしようもないじゃないですか。だからひたすら待ったらしいんだけど、結局8時間待ったって(笑)。
一堂 (笑)
富田 むしろ8時間経って迎えが来ることにビックリするじゃん(笑)。結局木村文洋の作品はその映画祭で賞を取って賞金がもらえることになったんだけど、あとで振り込みますって言われて、「ここでもらっておかないと絶対にもらえない!」って思ったから、粘りに粘ってその場で賞金もらって帰ってきたって(笑)。
「平成」というバブルの後始末の30年
三上 昨日の上映後のトークでは「平成という時代はバブルの後始末だった」という話も印象的でした。

富田 『サウダーヂ』で出てくるセリフでね、「バブルの後始末」って。虎ちゃん(富田監督とともに脚本を担当した相澤虎之助氏)が書いてきて、当時も「すごいセリフだ!」と思ったけど、昨日見たら前以上に染みちゃって。この30年は本当にそういう時代だったなって。原爆を落とされて戦後が始まって、高度経済成長とかいって、お金が余った素人たちが財テクだなんだって投機に出ていった。今から思えばバブルなんて危ない状態、いつか終わるのが当たり前なんだけど、当時はみんなそれが延々続くと思い込んでいた。それがある日ドーンと終わって、それからずっと後始末をしてきた時代が平成だったんだなって。
三上 それで景気が悪くなってエンタメ業界で博打を打つ人たちも少なくなっていき、売れるものをという画一化が進んでいった。
樋口 映画にしても、カサヴェテスとかフラーとか、バブルの時代じゃなかったら日本では見ることはできなかったでしょうね。
富田 誰も配給してくれないもんね、今は。
樋口 でも、たとえば自分のつくりたい映画を素直につくれる環境があったとしたら、空族が今のスタイルというのを確立できたかはあやしい。逆にいろんなハードルがあったからだんだんつくり方を変えていって、今がある。だから、どっちがいいかというのは難しい話なんだと思います。うまくいかないときって、自分が変われるかどうか、その現実にどう対応できるかじゃないですか。富田くんだってやりたい映画をつくれなかったときに、「やりたい映画」というだけで推し進めていたら、こうならなかったわけで。単にそこで潰れていたかもしれない。ダメだってときに、じゃあどういうつくり方があるかというのを考えて、何かが変わったと思うんですね。

三上 僕らの世代は最初から諦めてしまっている部分を感じます。生まれたときからオウム、阪神大震災とあって、小学校時代には9.11もあった。
富田 まさに世紀末…。
樋口 世界は終わるって感じだね。
三上 で、自分たちではよくわからないけど、ゆとり世代と呼ばれ。
富田 何のゆとりもないのにね。本当のゆとりなんて何もないのに。
三上 で、20歳になったら3.11。だから、僕の世代はけっこう暗いんです。何もいい話がない。だから、みんな現実的になるしかない。山梨に帰ってきて就職した友だちって、ほとんど公務員なんです。公務員以外は帰ってこない。僕みたいに、帰ってきて中小企業に勤める人間って周りに少ない。人と違うことをやろうって発想にならないように、飼い慣らされてしまっているような印象なんです。
地方はもう「保守」を選ぶことができない
樋口 昨日Twitter見てたら、20代の安倍政権支持率が70%だっていうんですよ。どうしてそうなってるのか、わかる部分とわからない部分があるんだけど、ちょっと思ったのは、そういう人たちにとってみたら、大人がわーわー騒いで安倍批判をしてるのって昔の政治のイメージにとらわれた人たちがもう一度何かをしようとして騒いでるようにしか見えないのかもしれないなってことなんです。ただの大人のロマンチシズムに見えてるんじゃないかって。
富田 俺たちは、地元とか地域のコミュニティから逃れたくて、そういうものがイヤで都会に出るという世代だった。都会に行って夢を見て、故郷に錦を飾るみたいな、そういう夢を見るギリギリの世代だから。ROCKスターを夢見てバンドブームに乗っかって東京に行くとかね(笑)。それで、地元にいると無尽(定期的に飲み会を行い、食事代などと別にメンバーの互助のための積立金などを支払う仕組み)だの消防だのというのがついて回る。とにかくそういうものがイヤで逃げ出したかったわけです。でも、最近は時代も、自分自身の認識も変わってきた。例えば今、買い物難民なんて話が出てきてるでしょう? 高齢になって買い物に行けない人たちの問題。でも、それって昔だったらコミュニティのなかで、何の決めごともつくらずに解消されていた問題なわけです。
三上 買い物に行くついでに近所の人が買ってきてくれる、とか。醤油の貸し借りとか……。
富田 そうそう。無尽や消防ってものも、そういう共同体を守る役割を果たしていたんだって今は思うようになっている。東京のように過密化した都市なら共同体がなくても生きていける。だけど、地方都市はそうはいかない。結局、均一化しすぎてしまったんだと思うんです。グローバリゼーションとかいって、どこもかしこも一律にしてしまったけど、それじゃダメだったんだ、と。
三上 3.11はそういう意味でもすごく象徴的でした。あの日、僕はオープンしたばかりの山梨のイオンにいたんです。
富田 えー! マジで!
三上 普段なら行かないんですけど、あの日はたまたま通りかかったんですよ。それで、3階にいたときに電気が消えて、揺れが来て……。そのときはそこまでたいしたことはないのかなって思っていたんですけど、家に帰ったら福島の映像が流れてきて。
富田 うわぁ、何かすごい話だね。

樋口 たぶんグローバリゼーションの限界みたいな危機感を肌身で感じているのは、東京以外、大都市以外に住んでいる人たちだと思うんです。彼らにとって切実なんだなって感じる。映画館の話だけど、爆音映画祭であちこち回っていても、本当にギリギリでやっているのは地方の映画館で、だからこそ変わろうともしている。一方で東京は全てが保守化している気がする。多分、まだ今の状態を守ればギリギリ生きていけるからということなのだと思うけど。
富田 あれもダメ、これもダメってね。
樋口 今自分が持っているものを守るにはどうすればいいかって考えてる。逆に今、沖縄があれだけ活発に動いているのは、沖縄が一番酷い目に遭っているんだろうなって。
三上 沖縄もすごいですもんね。スタートアップもたくさん生まれてて。スピード感が違う。
樋口 東京には未来がもう見えない。
三上 地方はもう保守的ではいられないんだと思います。保守がもうダメだから、選ぶことができない。
樋口 そうそう。地方はもう変わるしかない。変わるのが保守になっている。
富田 いいこと言うな~。ちょうどこの前、虎ちゃんが脚本で関わってる『菊とギロチン』って映画を見たんですよ。明治・大正のアナーキストたちの映画なんだけどね、それを見てアナーキズムってこういうことだったのかってわかったんです。つまり、自分たちのことは自分たちでやるっていうこと。それまでは、セックスピストルズのイメージが大きすぎて、アナーキストって、すぐに暴れだす人たちの事だと思ってた(笑)。アナーキズムを分かりやすく言えば、人間が寄り集まれば自然発生的にできあがる村落共同体みたいなものがある。それは大体顔の見える小さな範囲で成立している。それ以上の権力機関はいりませんっていうことで。確かにある地域で通用する仕組みだからって、別の地域に持っていったら通用しなかったりするでしょう? 気候や環境だって違うんだから。それを全部一律で決めましょうっていうのには無理があるだろうって。こんな小さな島国日本でさえそうなのに、アメリカだとか、中国だとか、あれほど広大な地域でひとつの国家だなんて無理に決まってるじゃん。そんな国どこにもないんですよ本当は。
三上 地方が持続可能な世界になるために、これからいろんな形で変わっていかないといけないですよね。今日は本当にありがとうございました!