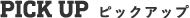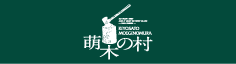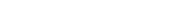「いらっしゃ~い!」。ジャズの流れる店内に、マスターの陽気な声が響く。ここは県道28号沿いにある魚料理店「魚ZENZOW」。8席ほどあるカウンター席が取り合いとなるほど、マスター・鈴木全(すずき・あきら)さんに会いたいお客さまがいる人気店だ。鈴木さんはROCKの店長として、「エキサイティングな毎日を送ってきた」と笑う。「ZENZOWに詰まっているノウハウのほぼすべてはROCKで学んだ」と言う鈴木さん。段ボールのメニュー表や、社長の涙…。濃密だった日々と、これからのROCKについて聞いた。

真っ赤なTシャツを着て、ポーズを決める鈴木さん
思いがけず店長に
―ROCKで働くようになったきっかけは?
横浜のステーキハウスで任され店長をやっていたとき、以前ホテルで一緒に働いていたN.Tさん(当時のROCK店長)に誘われたの。ちょうど妻と籍を入れ、第一子の出産も控えていた。家族で山梨に引っ越さないといけないから、2番手3番手(のシェフ)を育てるまでの1年か2年くらいなら、と奥さんの両親を説得して山梨に行くことになりました。
―ROCKに来ること自体に抵抗はなかったのですか?
全然。ROCKは10代のころからバイクで何度も食べに来ていたし、22、23歳くらいのときにもN.Tさんに誘われて一時期ハットウォールデンで働いていたの。まだたくさん工房がないころ。塚田(春夫・前ハットウォールデン料理長)さんや専務(舩木淳専務)ともよく話をしていた。萌木の村のこともROCKのことも分かっていたから、1、2年ならいいですって。
―以前から萌木の村との縁があったのですね。
でも、呼んでくれたN.Tさんが1年くらいで辞めちゃいました(笑)上次さん(舩木上次社長)が「おめえも辞めちゃうのかー」と言うから、「おれはまだ仕事を全うしていないから2番手3番手を育ててから辞めるよ」と言ったら、「そうか、じゃあおめえ店長やってくれえ」って言われて。「はあ!?」なんて言ってさ(笑)
―急ですね(笑)それで店長に。
それでいよいよ辞められなくなっちゃいました(笑)
毎日がエキサイティング!
―当時のROCK(2代目・ブルーパブレストランROCK)の印象はどうでしたか?
随分ばかでかいの造っちゃったなーという感じだった。旧ROCKが好きだったから。ああいうもっと茶色い空間になると思ったら、全面フローリングで、ゴルフ場とかホテルのロビーみたいに見えた。前のROCKには、上次さんや洋子さん(上次社長の妻)の思い出がぎっしりと詰まっていたから。おれぐらいが最後じゃないかな。旧ROCKの語り部ができるの。おれが旧ROCKも知っていて、新ROCKでも働いたちょうどの世代なんじゃないのかな。
―私自身、たくさんの方々のお話を聞いていると旧ROCKにタイムスリップしたいと思ってしまいます。
旧ROCKは薄暗くて、アメリカの物がいっぱい置いてあって。レコードのLP版って分かる?それがもううわあーってたくさん置いてあるレコードのお部屋があったの。そこでレコードをかけて店内で流していた。ロックとか、ジャズとかね。
―鈴木さんは都会の湘南ボーイズじゃないですか。それでも旧ROCKに来るのは楽しかったですか。
都会にはないROCK独特の雰囲気があったんだよー。やっぱり、別世界だったんだよ。細ーい急な階段を上って、がらがらって扉を開けると別世界になるの。

旧ROCK前で手を広げる10代の鈴木さん。大型バイクに乗り、やんちゃだった
―働き始めてからはどうでしたか?
1日2千人、カレーも1日800食ぐらい出していた。伝票がずらーっと2メートルぐらい並んでいるの。ご飯を炊く人はずーっとご飯を炊いていたし、キャベツを切る人はずーっとキャベツを切っていたし。深夜まで営業して「今からカレー作るぞ!」と言うと、みんな「えっ!!」って(笑)「タマネギ剥けー」「菊(後のROCK料理長・菊原和徳)、ニンジンー」とか言ってさ。
―深夜まで働きどおしだったのですね。
深夜からカレーを作ったり、次の日のステーキを切ったり。0時すぎまでやっていたもんね。「ほらー、早くやらないと朝になっちゃうよー」なんて言って(笑)ようやく0時、1時くらいに全部仕込みが終わって、そこからみんなでカラオケやラーメン屋に行ったりね。みんなへっちゃらだったよ。
-今は時代的にもそういった熱気がないので憧れもあります。
毎日エキサイティングだった。かじ取りがエキサイティングじゃないとやっぱりエキサイティングにはならないの。上次さんが精力的にエキサイティングだから、バレエでも村のことでもなんでもみんなついていこうって思うんじゃない。そういうところも上次さんに教わったよね。
でも、怒る時はガンガンうるさいんだよ。みんなで白い歯を出してにこにこしていると髪の毛がお皿の上に載っているのに持って行っちゃったり、異物が入っていたりしやすいからね。だから、料理や仕事に対しては真剣にしようと。でもそれ以外は真剣に遊ぼうよ、と。メリハリだよね。

ROCK店長時代の鈴木さん。毎日が忙しく、エキサイティングだった
―お客さんとの距離も近かったですか?
カウンターに一人で来る人が多かったの。ROCKの料理ってみんなボリューミーだから、一人だとおなか一杯になっちゃうでしょ。だから、おれが段ボールの裏に餃子とか焼き鳥、冷奴、枝豆なんかを勝手にマジックで書いてカウンターの人に出していたの。客足が落ち着いてくるとおれがカウンターに出て、雑談してさ。話し相手がいるから一人でも飲みに来てくれる。メニューにないものを勝手に売っちゃったりもしてね(笑)
―へえ。面白い仕掛けですね。
地元の人がちょっと立ち寄って飲む。そういうのが必要だよね。カウンターってやっぱりそういう役割じゃん。だいだいカウンターに一人ずつ座ると、カウンター同士が勝手に友達になっていく。ここ(ZENZOW)でもカウンターの七つか八つくらいの椅子が取り合いになっている。カウンターがいっぱいで遠くでぽつんと座っている人には、5分に1回くらい手を振ってあげる(笑)「見てるよー、大丈夫だよー」って(笑)
胸を突く言葉
―その後、独立された。
辞めるに辞められなくなり、40歳手前になった。住宅ローンを組めない年齢になるから、「上次さんごめんね、おれ住宅ローンも組みたいし、自分の店を出したいから辞めるよ」って言ったの。そうしたら、上次さんが「おめえいなくなっちゃうの嫌だな」と言って泣いてくれた。ROCKの2階の事務所でね。その時、上次さんの涙を初めて見たね。
―涙するほど大切な存在だったのですね。社長にはどのようなことを学びましたか。
もうね、お客さんありき。お客さんありき。いまだに言っているんでしょ、呪文のように。もうお客さんのために何ができるか、また来てくれるために何ができるか。「鳥の目、虫の目」っていう話を今でもよく覚えているよ。いつも小さな虫の目になって、ちり一つ、ほこり一つ、お客さんの目線一つ、細かく細かく見る。でも小さく見すぎているとグローバルな考え方ができなくなるから、時には高ーい上空を飛んでいる鳥の目になれって。それが鳥の目、虫の目。
―なるほど。分かりやすいですね。
ほかにも、「一人の人の後ろには20人くらいの知り合いがいると思え」っていうのもよく覚えている。それも上次さんが教えてくれたね。一人の後ろには20人、二人で来たら40人、ちゃんと目の前の人のために誠心誠意を尽くしてサービスを提供してあげると、その人はきっと20人に話してくれる。するとその人の後ろにはまた20人、また20人ってどんどんつながっていく。それって口コミでしょ。でも、口コミ、口コミってよく言うけど、そんな表現で言う人いないじゃん。誰が聞いても分かる。表現力がすごいよね。
―いまだに覚えているのですね。
毎日言われていたからね。しみ込んでいるよ。ZENZOWがこうやって活性化できているのは、上次さんの下で直属でやっていたっていうのがでかいよね、直球だったからねー。店長会(各店長のミーティング)では五味(辰弥)さん(次のROCK店長)とおれだけ、上次さんに面と向かってしゃべっていたの。「いや、それは違うと思いますよ」とか、平気でけつまくるようなこと言っていたから。そうすると、「おう。お前にはもっといい考えがあるんだっちゃか」とか言って始まるの(笑)

鈴木さんが考案した萌木の村のイベント「カントリーウエスタンフェア」(現在は行っていない)。催しの一つだった丸太をチェーンソーで削るチェーンソーアートにはまり、山梨県代表になったほどの腕前
50年のその先へ
―昨年はROCKが生まれて50年を迎えました。半世紀続いていることについてどう思いますか。
半世紀続いているのは、スタッフの努力だったり、社長の努力だったり、萌木の村の努力だったりもあるかもしれないけど、ROCKを愛してくれるお客さんがいたからです。あそこのことを愛してくれたお客さんがいた。全国にいた。おじいちゃんの代で来てくれていた人が息子さん娘さんと一緒に来たり、そのお子さんが生まれて、お孫ちゃんと来てくれたり。50年ということは3世代です。だから火事の後は全国からお客さんが応援してくれた。それに尽きると思うね。
―まさに「お客さんありき」ですね。もっとROCKが良くなるためには何が必要でしょうか。
やっぱりお客さんは放っておかれると寂しい。ここに来るとだれか知っている人がいると思うと来やすくなるんだよね。ROCKのカウンターってさ、あんなにたくさん席があるんだから、あのカウンターに3人も4人ものグループがこぞって行きたくなるようなお店を作ってあげなきゃ。カウンターって特別な席なんだよって。ROCKのタッチダウンビールのことをめちゃくちゃ語る人とか、べらべらずーとしゃべるような語り部みたいなスタッフがカウンターにいると、もっとビヤホールらしい場所になると思うよ。俺が仕事終わってから行ってあげようか、ROCKのカウンターの中に(笑)
―ぜひお願いします(笑)
時代もあるし仕方がない部分もある。でも本来、ROCKはビヤホールなんだからって。ビヤホールだよ。「ブルワリーレストランROCK」だよ。都会にあるようなキリンシティのビヤホールとかみたいに、もっとビールを飲みたくなるようなメニューを開発したりすると良いかもね。昔みたいにロックバンドの映像を店内で流して、わさわさした賑やかな演出をするのもいいかも。
―確かに。もっとビヤホールの印象が高められたら良いですよね。
もっと楽しいワードを取り入れればいいのに。そのためには音頭取りがいないと。音頭取りってね、ちゃんと成功体験を持っている人しかできない。最終形が映像化されて、カラーリングされていないと、途中のことをいくら話しても人はついてきてくれない。最後は絶対にこういう形になるからって最後までずっと言い続ける人じゃないと音頭は取れない。だから最終の色や形を分かっている人が店長をやらないといけないんだよ。
―今後のROCKに期待することはありますか。
ROCKの役割というのは、あそこを通過する人が、自立心をもったり、世界観が変わったり、卒業した人が一皮二皮剥けるような現場であってほしいな。弱かった自分が少し強くなれたとか、少し控えめだったのに積極的に動けるようになったとか。起業してみたくなったとか。そういう役割を持った施設であってほしい。
―鈴木さんはどうでしたか。
まさにそう。一番説得力あるんじゃないかな(笑)ZENZOWに詰まっているノウハウはROCKと上次さんで学んだことがほぼだから。
―貴重なお話をありがとうございました。
【編集後記】
「私たちの昔を見ているようだわ」―。
以前、洋子さんがZENZOWに来店した際、カウンターの賑わいを見て言ったこのひとことをよく覚えていると鈴木さんは繰り返しました。「今のZENZOWを見て、若い時の上次さんと洋子さんがROCKを始めたころを思い出してくれたことがすごくうれしかったなあ」(鈴木さん)。洋子さんの言葉から、ROCKに根付く思想がZENZOWをはじめ、さまざまな場所で今も漂っていることを知りました。
さて、8回目となる「ROCK歴代店長」インタビューでは、2代目ROCKを支えた鈴木全さんにお話を伺いました。ユーモアに溢れ、はつらつとした姿からは当時の活気あふれるROCKの熱気を感じるとともに、段ボールに書いたメニュー表のエピソードなどから、「お客様ありき」の基本を徹底しようとしていた気持ちが伝わりました。
規模もスタッフも大きく変わった現在のROCKですが、再びカウンターがいっぱいとなる日が来ることを願わずにはいられないのでした。
ZENZOWには新鮮なお魚を使ったお料理が揃っています。皆様、ぜひご賞味くださませ!
(取材・執筆 萌木の村広報室)