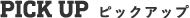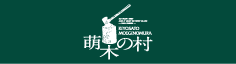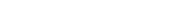萌木の村で社長の舩木上次が天才と呼ぶ人間のひとりが脇田直紀。萌木の村にある工房で、オルガネッタと呼ばれるオリジナルの手回しオルガンをつくったり、オルゴール博物館のオルゴールの修理やメンテナンスを行っている職人です。
その技術はもちろんですが、舩木上次が彼を天才と評するのは「ずっとひとつのことを続けている」という点。長年趣味で戦艦大和の大きな模型をコツコツとつくり続け、今では大和の研究家としても知られるほどになっていたり、ひたすらものづくりに打ち込む姿勢に舩木上次は惚れ込んでいます。
今回はそんな職人に経歴やものづくりへの想いを聞きました。今回はロングインタビューの前編として、幼少期からパイプオルガン工房での修業時代まで、萌木の村に来るまでのお話をお届けします。
興味がないことはやらないし、好きなことは止められてもやる
——社長(舩木上次)はいろんな人の話をしますが、そのなかでも突出して名前が挙がるのが脇田さんです。「ワッキーはすげえ」と。
社長は脇田病なんですよ(笑)。僕自身は何がすごいのかよくわかってない。勝手なことやっているだけなんで。ものづくりっていっても、ビールや料理だって、お客さんに喜ばれるものをつくってるわけだから、同じといえば同じだよね。
——僕たちも断片的には聞いているんですが、脇田さんが今までどういうことをしてきたのかという全体像を知る機会はなかなかなくて。今回は改めてそのあたりをうかがえればと思っています。
うーん、そうですね。もともと生まれは東京です。僕は1965年生まれ。新大久保で生まれたんですが、そこに住んでいたのは3歳くらいまでなのでほとんど記憶はないですが。はっきり覚えているのはその後町田市の玉川学園に引っ越してからですね。

脇田直紀。
——小田急線の玉川学園前駅のあたりということですか。
そうです。僕自身もその玉川学園って学校に通いました。ここは幼稚園から大学まで一貫教育をしている学校で、父が会社の知り合いに「面白い学校がある」と教わって、「じゃあそこに子どもを通わせよう」となったんです。で、どうせなら近い方がいいからということで町田に引っ越した。
——玉川学園ってどういう学校なんですか?
小原國芳という人が創始者の学校です。この人はもともと成城学園で校長をやっていたりしたんですが、そこでの教育は理想とズレてきてしまったということで、新たに土地を買って玉川学園を創設したんです。その理念が「全人教育」。偏った人間を育てるのでなく、勉強もできる、体育もやる、歌もうたう、芸術もやる。それで、そのなかから得意なものを伸ばしていくという理念なんですね。僕は幼稚園から、年子の兄貴は小学校からそこに通い始めました。そこに飾ってありますが、1枚だけ小原先生と撮った写真があるんです。

工房に飾ってある小原先生と少年時代の脇田さんの写真。
——あ、ここに飾ってある写真ですか?
はい。小学校入学のときの写真です。なぜなのかわからないんですけど、新入生代表に選ばれて挨拶したんです(笑)。小原先生は1887年(明治20年)生まれですから、もう当時かなりのお年だったんですが現役で、礼拝や何かで話をしてくれていました。みんなから「先生!先生!」って慕われる先生でしたね。ただ、話の内容は小学生だったからよく覚えてなかったんです。でも、45歳くらいになったころかな? なぜか突然小原先生の話を聞きたくなって。講話のCDなんかも出ていたので、それを取り寄せて改めて真面目に聞いたらとってもいい話がたくさんあるんです。それから何度も聞き返すようになりました。大した人なんですよ。学校をつくるっていうとお金持ちのやることというイメージですけど、この人はそんな資産家ではないから、借金まみれで学校をつくるんです。本を売ったり、質屋通いをしたりしながら暮らして、最終的にはあんな大きな学校をつくってしまった。パワフルで信念のある人なんです。
——新入生代表を務めたくらいですから、そこですごく優秀な生徒だったんですね。
いや、全然(笑)。どうも僕は学校の勉強っていうのが大嫌いで。特に中学校くらいまでは大の学校嫌いでした。面白くないんです。小学校なんか当然成績も悪くて。代表で入った人間が卒業の時には落第寸前っていうのは珍しかったらしいです(笑)。
——そうなんですか! 何がそんなにいやだったんですか?
なんでこんなことを勉強しなきゃいけないのかちっともわからなかったんです。これは今もそうで、わがままといわれれば返す言葉もないんですけど、好きなこと以外できないんですよ。逆に自分のやりたいことはどんなに反対されてもやる。極端なんですね。学校の勉強なんて全然興味がなかったから、いやでいやで仕方なかった(笑)。唯一美術だけでしたね、好きなのは。
——そのころから美術は好きだったんですね。
それも気付いたのは小学校3年生のときでしたが。それまでも美術の授業はあったんですけど、好きでもなかったし、得意だとも思ってなかった。そんなときに、夏休みの工作みたいな宿題が出たんです。何をつくろうかなって思ってたときに、兄貴が買ってきた戦艦大和のプラモデルが目に入った。僕はそのとき大和って戦艦がどういうものか全然知らなかったんですけど、「兄貴が買ってきたからこれをつくろう」って思ったんです。もちろんプラモデルを持っていくわけにはいかないから、木でつくることにして。当時は文房具屋さんとかでバルサっていう木材を売ってたんです。カッターで削れるような柔らかい木材で、それを使って大和をつくりはじめたんです。最初はそういう軽い気持ちだったんですけど、やり始めたらどんどん面白くなってきて。初めて自分の手でものをつくるっていうのが面白く感じたんです。で、やっているうちにどんどん細かいところまでつくり込んでいくようになった。そのとき初めて自分が細かいものをつくれる、器用だってことに気付いたんです。ものをつくる才能があるってことに気付いたきっかけになったんですね。
——小学校時代につくった大和の話は社長からもよく聞きます。できあがったものが今も玉川学園に飾られてると。
僕は見てないんですけど、「玉川学園の大学のエントランスのガラスケースで見たよ」って知り合いの大工さんに聞いたりはしました。僕の手元には写真もほぼないですね。小学校3年生ですからね(笑)。写真とか撮らないですよ。
——それで夏休みで大和をつくりあげたんですか?
いや、結局夏休みでは全然終わらなくて。最初は2〜3日でパッとつくろうってくらいの感覚だったんですけど、やっているうちにどんどん細かいところまでつくるようになって、結局半年かかりました。夏休みの宿題は別のものを提出して、そのあとも家でずっとやったり、それでも時間が足りないから学校でもつくったり。玉川学園って自由研究という独特の科目があったんです。個人の才能を伸ばすって理念で用意されてるカリキュラムで、好きなことを何でもやっていいという時間なんです。本を読みたければ読書してもいいし、絵を描きたければ描いていい、外で野球したければそれでもいい。その時間に大和を持ち込んでつくったり、何なら美術の時間にも勝手にやってました(笑)。そうしたら美術の先生も「なんだ脇田、スゲえのつくってるな」っていってくれて。結局4年生に上がる直前にできあがったんですけど、美術の先生が「この子はすごい!」っていってくれるようになったんです。担任の先生も算数の先生も、みんな「脇田なんて何もできない男だ」って思ってたんだろうけど、美術の先生だけは「こいつはすごい」「何年にひとりって人間だ」って褒めてくれた。だから、逆に美術の時間は適当にやると怒られるようになりました。こっちは楽しくやってたのに、「お前はこんなことしかできない男じゃないだろう」とかって(笑)。で、マジメにやると「すごいな!」って褒めてくれる。僕が大人になってからも、ときどき母が駅とかでその先生に会ったりすると声をかけてくれて「脇田くんは元気ですか」なんていってくれるそうです。
——その年齢の子どもが半年とか同じものをコツコツつくるっていうのがもうすごいですね。
あんまりないみたいですね。みんな2〜3週間もすると飽きるって。僕はやりたいと思ったらずっとやってしまうので。
楽器に興味がない青年が「すごい」と思った工房
——そこから本格的に美術や工作にハマっていったんですか?
もともと絵なんかも好きで、ずっと描いていたので、「そんなに好きなら」ってことで中学のときに親父が絵の先生を紹介してくれたりしました。家の向かいに芸大の先生がいて、美大を受験する人たちに絵を教えていたんですね。自己流じゃなくてきちんとした絵をその人に教わってこい、と。美大を受ける高校生のなかに中学生の坊やが入っていくわけですから、変な感じでしたけど、みんなかわいがってくれました。でも、そこでの勉強がまた面白くないんですよ(笑)。
——大好きな絵の勉強なのにですか?
さっきもいったようにわがままですから(笑)。自分が描きたいもの以外は描きたくないんです。ところが、そういうところってまずデッサンの基礎とかからやるわけです。石膏とかでできた立方体を置いて、「これを描きましょう」という。「脇田くん、絵っていうのは平面だけどこれがいかにも立体に見えるように、遠近法があって、光がこう当たって、影がこうあって……」って教えてくれるんですけど、一生懸命描いたって四角じゃないですか(笑)。次は球体が出てきて「今度は立方体と違って影がこうなって……」っていわれるんだけど、それも結局丸でしょ? 僕は汽車が向こうから煙をムワァ〜ッと吐いて迫ってくるような、そういう絵を描きたいわけです。下手でもいいから、自分でイメージした絵を描きたい。だから、つまらなくて先生がいなくなると美術の本を読んだりして時間を潰してたんです。そのうちに「脇田くんは絵が好きって聞いてたんですが、なかなか描かないですね」って追い出されて(笑)。親父は「やっぱりこいつは自己流でやってるだけで世間で美術で食っていけるようなやつじゃないんだ」って気付いて、よけいに勉強しろ勉強しろってうるさくなった。だから、行かなきゃよかったって思いましたよ(笑)。結局人にカリキュラムとか決められてこれをやれっていわれるのがいやなんですね。自分のやりたいことをやりたいようにやりたい。
——パイプオルガンやオルガネッタに出会ったのはいつなんですか?
高校に入ってから多少勉強をするようになって、大学にも行けるだろうってくらいになったんですけど、僕自身は美大に興味がなかったし、一般の大学に行ってまた勉強するなんていやだった。そんなときに、辻宏さんという方の工房に行く機会があったんです。実はこの辻さんの奥さんが、以前父の同僚で、玉川学園を薦めてくれた方なんです。で、その辻さんは日本で一番最初にパイプオルガンをつくった人で、神奈川県の座間市に工房をかまえていた。でも、住宅地ですからどうしても騒音が出たりしてやりづらいということで、友人に紹介してもらって70年代の半ばに岐阜県に工房を移したんです。山のなかにあった廃校の校舎を工房にしてね、そこでパイプオルガンをつくっていた。ときどき東京に来るとうちに立ち寄ってくれることもあって、僕も「面白そうな仕事だな」と思っていたんです。僕はものづくりが好きなんですが、工場でものをつくることには興味がなかったんですね。自分の手でオリジナリティのあるものをつくりたいという気持ちがあった。そう思っていたときに、岐阜にある辻さんの工房に行ったら、山のなかにある校舎を全部工房にして、まわりの木を切って製材するところから、何万点何十万点という部品を手づくりしてパイプオルガンをつくっているんです。パイプオルガンの笛は鉛やスズを使ったりするんですが、これは融点が260〜270度と低いから鍋に入れて火にかけると溶けちゃうんですね。だから、辻さんの工房では給食室の鍋で溶かしたりしてたんです。「ここはあらかじめいろんな設備があって便利なんだよ」なんていって(笑)。僕はパイプオルガンはもちろん、楽器自体まるっきり興味がなかったんですが、「これはすごいぞ!」って思ったんですね。それで家に帰ってきてから親父に「辻さんに弟子入りしたい」といったんです。
——楽器に全然興味がなかったのに?
ある意味では、ものづくりはしたいけど、そのとき知っているものづくりのあてが辻さんしかなかったんですよね。だから、将来パイプオルガンをずっと続けるか、そこで技術を身につけるのかっていうのはわからなかったけど、とにかく興味を持ってしまった。親父は「今は見てきたばかりだから盛り上がっているだろうけど、苦労するぞ」とか「金にならんぞ」っていうわけですが、興味を持ったらそんなの耳に入らないですから。「せめて大学を出てからにすればいいだろう」ともいわれたんですけど、やりたいことがあるのに行きたくない大学に行くなんてもう考えられないんです。辻さんもお弟子さんは何人もいたけど、みんな楽器やパイプオルガンが好きで入ってくる人ですから、僕みたいにパイプオルガンには全然興味がないなんて人はいないわけです(笑)。「ものづくりが好きっていっても続くかね……?」なんて渋い顔してたんだけど、「とにかくものづくりが好きで器用だから、楽器が向いているかわからないけど、使ってお役に立つこともあると思うんで入れてやってください」と親父が頼んでくれて、それで「やってみましょうか」と入れてもらえることになった。それで18歳のときに岐阜の辻さんの工房に行ったんです。
ツラいことを続けたから大成したのでなく、ただ楽しいことをやっているだけ
——行ってみてどうでしたか?
入った途端に「これはとんでもないところに入ったな」と思いました(笑)。まず技術のレベルが違う。僕はものづくりなら誰にも負けないって自負があったんですが、あたりまえですけど、こどもの「工作がうまい」というのと職人の技術じゃ桁が違うわけです。さらに、使う言葉が全然わからない。パイプオルガンってもともとヨーロッパの文化なので、膨大な部品のひとつひとつがみんなドイツ語とかだったりするんです。だから、会話を聞いていてもさっぱり理解できない。素材の知識もないでしょう? 今はみればどれがさくらでどれが楢かとかだいたい見当が付くけど、当時は全然わからないですから。先輩が製材して出た端材を片付けるんですけど、さくらのところに楢の端材を並べてしまったり、「もう使えないだろう」と思って本当は使える端材を捨ててしまったり。
——最初はわからないですよね。
それで怒られたりしながら少しずつわかるようになっていきました。あと刃物の手入れなんかも大変でしたね。職人の道具っていうのは自分で手入れをしないと使えないんです。だから、ひたすら刃物研ぎをするんですけど、これが難しいんですよ。うまくなるのに10年くらいかかる。2〜3年でどうにか使えるようなものができるようになったんですけど、冬にやっていると寒くて指先の感覚がなくなるんです。岐阜の工房は寒かったですから。標高は500mくらいでしたけど、平気でマイナス17度とかになってましたし、工房も古い校舎だからガラスは薄いし、隙間もたくさんある。そんななかで刃物研ぎをやるわけです。刃物研ぎってなるべく刃先に指を当ててやるんで、いつの間にか刃じゃなくて指を研いじゃってたりするんです。で、砥石にスーッと血の線が付いて。切るんじゃなくてすり減ったものだからなかなか治らなくて痛いんですよ、これが(笑)。交代で炊事をやるんですけど、そのときにも染みてね。給料も安いから、最初は手取りで7万くらいだったかな。当時の最低賃金でした。最初は高校を出たばかりで、それまでお小遣いでやりくりしていたから「こんなにもらっていいの!?」なんていっていたけど、すぐに慣れて「なんでこんな安いんだ」とか文句いうようになってました(笑)。
——大変な生活ですね。
今から思うとね。でも、こういう話をすると「苦労したんですね」っていわれるんですけど、そんなに苦労したって感覚がないんです。もちろん「風呂がボタンひとつで炊けたらな」なんてことは何度も思いましたけど(笑)、自分としてはとにかくやりたいことをやっていたわけですから。イチローとかもそうですけど、小さいころから毎日何時間も素振りをしたり走り込みをしていたって話が出てくるじゃないですか。そうするとみんな「やっぱりツラい努力をしたんだ」「大成するにはそういう大変さに耐えないといけない」って思っちゃうんだけど、たぶん本人はそんなに大変じゃなかったと思うんです。遊びに行くよりそうやってる方が楽しかったんじゃないですか? ただ面白いと思うことをやっていただけなんですよ。僕もそうで、大きな木を製材して部品にしていくとか、そういうことがとにかく面白かった。木のこともだんだんわかってくるし。木って面白いんですよ。もともと生きていたものだから、ひとつひとつクセがあるし、方向によって強度も変わる。柾目とか板目っていうんですけど、木の中心側で年輪の層がギュッと詰まってるのが柾目、外側で木の模様が現れているのが板目です。強度も違うし、それぞれ強い方向がある。だから、例えば梁なんかに使うとき、方向を間違えて使うと重さでたわんでしまったりするけど、逆に正しく使えばずっと曲がらず強いままなんです。法隆寺とか古い建造物なんかは、木材が木だったとき南側を向いていた方を南にしたりしてるんですね。もともと生きていたものだから、よく日が当たる南側はそれに適した組成になってる。そうやって自然の摂理に沿ってつくってあるから、千年以上たっても修復すれば残るほど強いものになってる。

湿度によって収縮するのも木の特徴のひとつ。乾燥した時期は木が縮み隙間が空きます。湿度が適度な時期にぴったり合うように計算してつくる必要があるんです。
——奥が深いですね。
めんどくさいともいえる(笑)。切ってきてから乾燥だけで何年もかかりますしね。でも、そこが面白いところで、そうやってひとつひとつクセがある素材を見て、どこに使おうって考えて部品をつくっていくのが、いかにもものづくりをしているって感じで楽しいんですよ。
確信が持てないとき、人は迷う
——オルガネッタをつくりはじめたきっかけは何だったんですか?
20歳くらいのときだったかな? 辻さんのところに手回しオルガンみたいなものをつくってくれないかって話が来たんです。田舎なので大した産業がなくて、辻さんの工房はひとつの名所みたいになってたんですね。工房なのに観光バスが来たりすることもありましたから。だから、せっかくなら工場でできるようなお土産みたいなもの、オルガンのおもちゃみたいなものを考えてもらえないかって相談が来たんです。それで辻さんがヨーロッパに紙に穴を開けて音が出る手回しオルガンみたいなものがあるらしいから、誰か考えてみないかって持ちかけたんです。先輩たちは興味がなかったのか思い付かなかったのか誰も手を上げなかったんですけど、僕は「面白そうだな」と思って。まあ、懸賞金が5万円出るっていうからそれがほしかったのもあるんですが(笑)。それでいろいろ考えて試作品をつくったんです。

初期のオルガネッタのスケッチを見ながら。
——それはいつくらいのことですか?
第1号ができたのは1987年かな。それはおもちゃみたいなものです。そのとき僕は自分で笛をつくることができなかったんで、先輩がつくった笛をお借りして載せて、それ以外のところを自分でつくった。アコーディオンみたいな“ふいご”があって、それを広げると自重で閉じていくんですね。そのとき出る空気を紙に開いた穴を通すことで、通る笛を変えるというシンプルな仕組みです。4〜5秒しか鳴らないものでしたけど、とりあえずちゃんと音が出るものになりました。結局商品化はされませんでしたけど、「すげえ! ちゃんと鳴るじゃねえか!」ってことで懸賞金をいただきました(笑)。その次はハンドルを使った手回し式で、笛も増やしたものをつくりました。いつまでも笛を借りているわけにいかないから、先輩に教わって笛も自分でつくるようになって。性能が安定しなかったから2〜3年かけて改良していってだいぶよくなったんだけど、結局これもものにならなかった。どうしようかなって思いながらつくった3台目がこの工房にあるオルガネッタです。

工房に置かれた3台目のオルガネッタ。
——あ、これですか。
そうそう。当時ちょうど銀座で音のアンティーク展というのをやっていて、オランダにある世界屈指のオルゴール博物館からもいくつかのコレクションが出展していたんです。僕は行けなかったんですけど、親父がたまたま行ったらしく、そこで本を買ってきてくれた。そこに載っていた楽器を見て「かっこいいな!」と思って、それをアレンジしたイメージスケッチを描いたんです。笛の音といっしょに太鼓が鳴るんですけど、太鼓は工房に転がっていたバターの缶を使ってます(笑)。最初につくったものって、そういう寄せ集めとかインスピレーションの塊なんです。
——今の脇田さんのオルガネッタの原型ですね。
ただ、これをつくろうと思った時はどうしても仕組みがわからなかった。これは空気を送るところに直接紙を置く仕組みではなくなっているんですけど、じゃあどうやれば演奏ができるのかっていうのがわからない。辻さんの工房はタンスくらいの小さなものから教会に納めるような大きなものまで、いろんなパイプオルガンをつくっていたけど、鍵盤を使ったもので、紙に穴を開けて演奏するようなものはつくっていないわけです。だから、笛やケース、ふいごのつくりかたは習ったことをそのまま使えるけど、紙で演奏する方法はわからないんです。で、試行錯誤しながらいろいろ考えて、かなりいいところまでいったんですが、あと一歩うまくいかない。そうなると迷うんです。正解がわからないし、資料もないでしょう? だから、自分が完成に近づいているのか、見当違いのことをやっているのかわからない。いいところまでいっていると思っても、そのままこの発想を煮詰めればいいのか確信が持てない。そのうち、このままこんなことやっていても時間の無駄じゃないかとも思えてくるんです。3年くらい試行錯誤して行き詰まってましたね。
——突破口は何だったんですか?
何か資料がないかってことで東京のオルゴール博物館に行ったんです。で、こういうものはないかって聞いたら「うちにはないけど、最近清里にできたオルゴール博物館に手回し式のオルガンがあるよ」って教えてくれたんです。

最初のイメージスケッチ(下)と、インスピレーションの元になった楽器(上)。
——萌木の村のホールオブホールズですね。
そうです。それでさっそくここに来て、小さな手回し式のオルガンを見せてもらったんです。中を開けてもらって見た瞬間に構造がわかりました。結果からいえば、僕がつくっているものと構造は同じだったんです。ただ、部品の形や材料が違っていたからうまくいかなかったんだ、というのがパッとわかった。もう嬉しくて! 「これでできる!」ってわかって、すぐに岐阜に帰ったんですけど、興奮しててその道中のこと全然覚えてないんです。危ないですよね、清里から4時間も運転してるのに(笑)。それくらい頭に血が上ってた。
「鳴らすのが難しい笛」を選んだことがプラスになった
——それでこのオルガネッタができたんですね。
はい。それが1990年です。
——演奏も聴かせてもらいましたけど、これ、すごくいい音ですよね。
そうなんですよ。すごく音がいいんですよ、こいつ。でもこれ、最初は全然音がよくなかったんです。辻さんにも「よくできたね! でも、音はあんまりよくないね」なんていわれてたくらい(笑)。でも、あるとき急に音がよくなったんです。
——え、何がきっかけで?
いや、それがわからないんです。楽器ってエージングなんていって、鳴らし込むとだんだんいい音になったりするんですが、そういうものはジワジワ変わっていく。これはある日急にいい音が鳴るようになったんです。僕も理由がわからなくて、変な言い方ですけど、神様がイタズラしたとしか思えないんですよね。僕は今45台目のオルガネッタをつくっているんですが、そのなかでもベスト5に入る音だと思います。
——やっぱり熟練してもそういう個体差みたいなものはあるんですね。
あります。さっき木の話もちょっとしましたけど、素材自体もひとつひとつ違うし、全部手づくりですから。もちろん最近はだんだんうまくなってきて、音をコントロールできるようになってきたし、質も安定してきたけど、そもそもひとつひとつ違うし、最初の頃なんか特に安定しなかった。実はあとになってわかってきたんですが、この笛ってすごく鳴らしにくい形だったんです。最初にイメージスケッチを描いたとき、僕は笛のことなんて全然わかってなくて、単に丸めて半田付けして、くらいしか知らなかった。笛の寸法をどうすると音がどう変わるかなんてこともわかってなかった。だから、見栄えのいいようにって感じでイメージスケッチを描いちゃったんですね。で、それに合わせて試しに1本笛をつくってみたら、たまたま鳴ったんです。しかもけっこういい音で。だから「これでいこう!」ってなってしまったんですけど、最初に鳴ったのは本当にたまたまで、この笛っていい音どころか鳴らすこと自体難しい形だったんですよ。最初のうちは鳴らすこと自体難しくて、先輩のところに持っていっても「こんな笛鳴らせるか!」っていわれるし(笑)。辻さんもこんな寸法の笛はやったことがなかった。たまたまイタリアの古い楽器の修復を頼まれたとき、似たような寸法の笛があったんですね。それで、その笛がいい音を出していたから採寸して自分のオルガンにつけることにしたんですけど、辻さんもなかなか鳴らなくて、散々苦労していた。

バター缶を利用してつくった太鼓。実際に鳴ります。
——ものすごくハードルの高い形を選んでしまったんですね……。
でも、後付けの結果論かもしれないですけど、簡単な笛をやっていたら今みたいな技術は付かなかったと思うんです。僕は辻さんに笛の鳴らし方ってほとんど習っていないんです。なのに、すごく鳴らしにくい笛を最初につくってしまったから、どうにか鳴らさなきゃって自己流で四苦八苦して鳴らせるようになって、今度はいい音を出せるようにって試行錯誤して……そうやっているうちにいつの間にか笛を鳴らす技術がずいぶん上がっていた。辻さんは2005年に亡くなられてしまったんですが、晩年筋萎縮症っていう病気にかかって、車いすに座って指を動かすのもやっとみたいな状態になっていたんです。そんなときに、大きなオルガンを地元の音楽ホールにつくる仕事をやっていたんですね。お弟子さんがいるから部品やケースは指示をしてつくることができる。でも、最後音を鳴らす部分はそのときできるお弟子さんがいなかった。もちろん辻さんの身体が動いたころは、自分でオルガンのなかに潜っていって整音していたんですけど、身体が動かないからそれもできなくなってしまった。それで、辻さんのところを辞めて十数年経っていた僕のところに連絡が来たんです。で、僕がオルガンに潜り込んで整音したんですが、それを見ていた辻さんが驚いて「僕は君に笛の鳴らし方教えてないよね。どこでその整音技術を身につけたんだい?」っていってきたんです。「いや、どこというわけではなく自己流です」といったらえらい驚かれて。あとで奥さんに「「脇田くんは素晴らしいヴォイシング(整音)技術を身につけていた」って話していたそうです。鳴らしにくい笛を相手に四苦八苦しているうちに、いつの間にか技術が身についてしまったんですね(笑)。
——学びがあるわけですね。
「禍転じて」ってことだよね。もちろん禍のまま終わってしまうこともあるんだろうけど(笑)。でも、必ずしもいいふうになるとは限らないにせよ、振り返ってみると自分の場合はプラスになったことが多いんです。このオルガネッタに使っているハンドルもそうです。最初は何かちょうどいいものを買ってこれないかと考えて探していたんです。それでアンティークのコーヒーミルのハンドルでちょうどいいものを使っている喫茶店を思い出して、その喫茶店に譲ってもらえないか相談したりもしました。でも、結局譲ってもらえなくて、仕方なく自分でつくることにしたんですね。でもこれが、木でつくってみると収縮でだんだん歪んでしまう。このオルガネッタはもともと何台もつくる予定はなかったので、あのミルを譲ってもらえればこんな苦労はしなかったのにと思ったんですが、結果として断られたから自分でつくるようになって、今ではちゃんとつくれるようになった。だから、その後注文が入っても対応できる。そのときは悔しかったけど、今から思えば譲ってもらえなかったことがプラスになっているんです。

自作した手回しハンドル。最初につくったものは歪んでしまっていたが、現在はきれいなハンドルができるようになったそうです。
——経験は無駄にならないですね。
僕は何でも自分で思ったとおりにやってみないと納得できなくて、教わったとおりにやるっていうことをやっていたのは、辻さんのところにいたときだけなんですよね。それも辻さんのいったことでも違うんじゃないかって思ったら自分流にやっちゃう。それで辻さんに怒られてた(笑)。辻さんは正解を知っているわけです。先輩たちは正解を教えてもらってそのとおりにやっている人がほとんどなんですね。でも、僕は正解を知らないけど、自分が思ったようにやってみないと気が済まない。いわれたことをやるにしても、「この方がいいんじゃないか」って思ったらやってみないと納得できないんです。当然失敗して、結局辻さんの方法に行き着くんだけど、そういう回り道をすると「なぜこれをやってはいけないか」というのが骨身に染みてわかる。もちろん辻さんも説明はしてくれるんですけど、聞いただけだとなかなか身に染みて理解はできないんです。で、そのときは失敗なんだけど、そういう発想や着眼点が別のところで化けたりする。ものづくりってそういういろんな経験のストックが重要なんだと思います。今もアニメに出てくるからくり時計をつくってほしいっていわれてつくっているんですけど、あちこち「こんなのどうすればいいんだ?」ってところが出てくるんです。そういうときに、自分のなかの引き出しから「こうしたらいいんじゃないか」っていうのを出してつくっていくんですね。
イメージの湧かないものはいいものにならない
——ここにあるのがその時計ですか?
そうです。注文を受けたのはもう7年も前ですね。でも、実際につくりはじめたのは2年くらい前です(笑)。
——5年は何をやってたんですか?
これってもともと僕がつくりたいと思ってつくりはじめたものじゃないんですよね。最初に連絡を受けたときもピンと来なかったし、僕も別に時計の専門家ではないですから、渋っていたんですけど、「いろんな人に頼んで断られている。何とかできないか」っていわれて「まあ、じゃあ」って引き受けたんですね。でも、自分がつくりたいわけじゃないものって、イメージが湧かないんです。これなんてもともとアニメで描かれたものですから、僕のものじゃないんですよね。だから、まずはスケッチを描いて工房のいつも見えるところに貼ったんです。それで毎日チラチラ見ていると、最初は「なんだかなぁ」って思ってたものが、徐々に「ここはこうか?」「意外と悪くないんじゃないか?」って思えるようになってくる。つまり、自分のなかのイメージができてくるんです。それで改めて「こういう形でどうですか」って送って、やりとりをして徐々に実際の形を固めていったんです。アニメなので、シーンによって形が変わったりするんですよ。だから、それをどっちにするかとか、この形にするならここはこう変えた方がいいとか決めていって、イメージに合わせるためにアニメから変えた部分も出てくる。逆にいうとそこでアニメのものから僕のものに変わっていくんですね。5年間はそういうイメージをつくるためにかかった時間なんです。

製作中のからくり時計の時計部分の試作。ギミック部分は試行錯誤しながらつくっています。
——イメージって大事なんですね。
イメージが湧かないものってつくれないんです。それってビールなんかも同じじゃないかなと思います。「こういう味に仕上げよう」「こういうお客さんに飲んでもらおう」ってイメージがあるからできるわけでしょう? どこかで教わったり勉強したものと違って、オリジナルのものって自分のイメージがすべてですから。そういうイメージがあってつくるものは完成度が高くなる。逆に世間の流行りだから仕方なくつくるってものは、結局いいものができないんですよ。だってものをつくるってめんどくさいですから(笑)。自分がつくりたくてつくるものは、めんどくさくてもこだわってつくるわけです。でも、仕方なくつくっていたら、どうしても「これくらいでいいか」って部分が出てきてしまう。こだわりがなくなるんですよね。
——脇田さんのものづくりは「つくりたい」というのに忠実ですよね。
さっき工場でつくるものは惹かれないって話をしましたけど、あの話にも通じているんです。例えば車なんかって、もちろんメーカーさんにはいいものをつくろうってポリシーはあるでしょうけど、同時に企業であり商品なので、売れるものをつくらないといけない。そこで収益を上げないといけない。だから、流行の形や色を取り込んでつくっていくわけです。純粋な機能とか性能、あるべき姿だけを追求した形ではない。それって「生産」という感じなんですよね。僕は小学校3年生のときに戦艦大和をつくってから、すごく戦艦が好きになったんです。零戦なんかもそうなんですが、調べれば調べるほど美しいと感じるんですね。「兵器なのに」って思われるかもしれないですけど、僕からすると山や渓谷、自然の景色が美しいと思うのと同じように「美しい」と思うんです。
——自然と同じようにですか?
そうです。兵器って、いうのは見た目がかっこいいこととかどうでもいいんです。強くなくちゃいけない。そこに求められるのは極限の性能なんですね。だから、大和や零戦って贅肉がまったくない。大和って7万トンの戦艦なんですが、設計図を見ると数百グラムの肉を削って削って仕上げてるんですね。よく「7万トンもの巨大な戦艦」っていわれるんですけど、そうじゃない。削って削って7万トンになっているんです。だから「よく7万トンに抑えたな」というのが本当のところなんです。そして、すべてのバランスが取れていないと性能は上がらない。バランスっていうのはつまり、自然の摂理に沿っているってことです。水の上を走ったり空を飛んだりするわけですから、自然の摂理に沿わないといけないんです。自然の景色はいわば神様がつくった芸術ですけど、大和や零戦は人間が自然の摂理に沿ってつくった芸術だと思います。楽器なんかもそうでしょう? バイオリンなんかはもう何百年も前からあの形じゃないですか。科学や技術がすごく進化しても形が変わらない。それまでいろんな形でつくられて、行き着くところまで行き着いて、もう足すことも引くこともできない形になったのがあれなんです。大和や零戦も同じで、極限の形を日本人の感性でまとめ上げているんだと思います。
——究極の形ということですね。
しかも、あの時代だからこその面白さがあるんです。大きなものって工業力がないとできないんですが、同時に工業的になりすぎると無機質で面白くなくなってしまう。大和や零戦がつくられた時代って、それだけ大きなものをつくれる工業力ができた時代で、同時に職人芸も残っていた。そのふたつが合わさってできたのが大和や零戦なんですよね。だから、最初に出会った小学校3年生のときからもう40年以上になりますけど、いまだに写真を見ていて飽きない。

脇田さんがつくっている戦艦大和の模型の写真。パーツひとつひとつが手づくりです。
——脇田さんはライフワークとして何十年も戦艦大和の模型をつくっているんですよね。
それは完全に趣味ですけどね(笑)。今もいろんな素材を使ってひとつひとつパーツをつくっています。部品をつくるたびにどうすればいいか試行錯誤して、失敗しては知らない素材を使ったりしてます。できない日もありますけど、だいたい毎日やってますね。
——萌木の村に来るまでの話でずいぶん長くなってしまいました(笑)。次回、改めて萌木の村へ来た経緯などをおうかがいできれば!