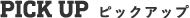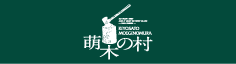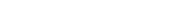さまざまなスタッフが支えているROCKと萌木の村。なかでもその顔をつくっているひとりといえるのが、工房モルゲンロートの小林雅之さん、通称「モルゲン小林さん」です。
モルゲンさんは萌木の村のさまざまなディスプレイをつくったり、写真を撮ったりと、萌木の村の景色づくりに大きく関わっているスタッフです。実は昨年スタートしたInstagramの写真の多数を撮っているのもモルゲンさん。ものづくりから写真など、さまざまな形で関わる萌木の村にはなくてはならない存在です。
今回はそんなモルゲンさんに話を聞きました。
「山で生活したい」から始まった清里暮らし
——モルゲンさんは萌木の村でいろいろな仕事をしていますが、そもそも関わるようになったきっかけは何だったんですか?
もうずいぶん昔の話になりますが、31年前、大学生だったころにこのあたりをバイクでツーリングしていたんです。当時僕は美大にいて、工芸デザインをやっていたので、萌木の村の存在も知っていました。その当時の萌木の村って今以上につくり手の場所で、今の萌木窯さんみたいな工房が集まっていたんです。銀細工の工房とか革細工の工房とか、ドライフラワーの工房……みんなそこでものづくりをしていて、オーナーがそれを売っていた。だから、そういうことに興味があった人間としてふらっと立ち寄ったんです。そのときはレザークラフトのお店に立ち寄りました。 それでいいところだなぁって。僕はもともと山が好きなんです。

工房モルゲンロートの小林雅之さん
——そうなんですか。
実家は埼玉県なんですが、中学生くらいのときに友だちが山岳同好会みたいなものに入っていたんですね。僕は同好会に入っていなかったんですけど、友だちについていく形で丹沢の沢登りに行って。それがきっかけで山が好きになりました。大学は自分のやりたかった金属の学科がある金沢の美大に行ったんですけど、半分「山にも登りたい」という不純な動機もあったんです(笑)。北陸は北アルプスに近く自然も豊だったので。それで大学で山岳部に入って本格的に山登りを始めて、実家に帰るついでにこのあたりもふらふらするようになっていたんです。
——そんなときに萌木の村に立ち寄ったんですね。
そうです。それで単純に「こんなところで作品づくりができたらいいなぁ」って思ったんです。作品づくりの環境もですけど、山で生活したいという気持ちがあったので(笑)。金沢ってやっぱり実家と行き来するには遠いんですよね。清里だと山があって、雪があって、しかも東京や埼玉の実家も近い。すごくいい場所だったんです。そんなことを思いながらふらふらしていたら、「なら、(萌木の村の社長である舩木)上次さんって面白い人がいるから会ってみたら?」っていわれて。それで会ってみたらトントン拍子で話が進んで、ここで働かせてもらうことになったんです。本当に巡り合わせですね。
——じゃあ、ものづくりをするために萌木の村に来たわけですね。
だけど、そうはいっても当時はまだ作品もなかったですし、いきなりここでものを売って生活することはできないじゃないですか。だから上次さんが「お金に困るだろうから(萌木の村のホテル)ハット・ウォールデンで働け」っていってくれて。それで、ホテルで働きながら小さなプレハブに仕事場をつくって金属細工なんかをつくったり、写真を撮ったりしていました。結局ホテルでは7~8年働きましたね。
——ホテルにいたというのはなんだかすごく意外です。イメージになかったというか。
実際接客なんてバイトくらいでしかやったことがなくて、真剣にお客さんと向き合うというのは初めてでした。それこそフルコースのディナーなんて食べたこともないようなタイプでしたし。でも、それもすごくいい経験でした。知らないことを知ることができた。
場所や空間をプロデュースすることとの出会い
——今のような仕事をするようになったきっかけは何だったんですか?
実は大きな転機というのはやっぱり来てすぐのころなんです。僕がここに来た年に(キープ協会の)「ポール・ラッシュ祭~八ヶ岳カンティフェア~」が始まったんです。内容もいろいろ趣向が凝らされていたんですけど、あれは装飾もすごく凝っていた。たとえば、今はこのあたりで牧草といったら(大きなタイヤ状の)牧草ロールですが、当時はまだロールの形のものはなくて、キューブ型のものが一般的でした。その牧草キューブを会場に飾っていたんです。そういう会場のプロデュースをカントリーイン オーチャードハウスのホテルの出口さんが担当されていました。この出口さんのプロデュースに感銘を受けたんです。出口さんのコンセプトは「田舎暮らしのかっこよさ」というものなんですけど、いい言葉ですよね。すごく面白かった。
——会場のプロデュースというわけですね。
そうです。それで、第2回のとき「入場門みたいなものが欲しいよね」という話になったんです。そこで僕がこんなのどうですかって、牧草キューブを重ねたような形のアーチを提案をしたんです。牧草は重くてそのまま積み重ねてアーチにすることはできないので、ベニヤで空洞のアーチをつくってそこに牧草を貼り付けるような形で。本物を使ったイミテーションみたいなものですね。タッカーっていう大きなホッチキスみたいな道具で本物の牧草を付けていく形にしたんです。これがすごくうまくいって、みんなが本物の牧草キューブでつくっていると思うようなものができた。このアーチは31年たった今も同じ形で続いています。このときみんなに受けたというのがきっかけで、こういう仕事って面白いなと思うようになったんです。つまりイベントとディスプレイづくりですね。

カンティフェアで設置されるアーチ。31年前にモルゲンさんがつくった形が今も踏襲されています。
——ちょっと珍しいというか、あまり思い付かないものづくりの形ですよね。
はい。いわゆる作品じゃなくて、アイディアを見せるような形ですよね。それって作品をつくる以上に純粋にお客さんに見てもらって、受け入れてもらうことができる。その喜びというのはすごいなと思ったんです。
——それが今の仕事の原点というわけですね。
そうですね。それとそのあと清里フィールドバレエ(萌木の村で毎年夏に行われている野外バレエ)にも関わるようになるんです。フィールドバレエが始まったのは僕が来た翌年なんですが、最初はまったく関わっていなかったんです。だけど、フィールドバレエはだんだん規模が大きくなっていって、使う道具も多くなっていった。それで、3回目の開催のときに演目上どうしても大きな家の絵が必要になったんです。そうしたら上次さんが僕に「お前、美大を出てるんだから描けるだろう」っていって、それでいきなりバレエの大道具づくりを任されちゃったんです(笑)。
——上次さんらしいですね(笑)。
でも、そのときは純粋に嬉しかったですね。ホテルの仕事も一生懸命やっていましたけど、やっぱりそういうものづくりをしたかったんで。それからフィールドバレエに携わるようになって、年々必要なものも増えていき、関わることも多くなっていったんです。同時に萌木の村のなかでもいろんなデザインであったり、つくるものが多くなっていった。徐々にいろんなものをつくるようになっていって、それで7~8年目に独立することにしたんです。独立といっても萌木の村におんぶに抱っこみたいな形でしたけど、オルゴール博物館の下に土地を借りて、仕事場をつくらせてもらった。そこを拠点に年間の半分は萌木の村の仕事、もう半分はここでできたつながりもあったので、大工さんなんかに仕事をいただいていろいろつくるようになりました。

冬になると萌木の村の広場に設置されるトナカイもモルゲンさんの手がけたディスプレイ。
萌木の村だからできた「アート」の生活
——そのあたりで今のモルゲンさんのスタイルができたわけですね。それにしても、モルゲンさんの仕事ってすごく幅広いですよね。素材にしろつくるものにしろ……
萌木の村ではディスプレイ全般ですからね。だから、子どもに「お父さんは何の仕事?」って聞かれたことがあるんですけど、非常に答えづらいんです(笑)。何をやってるって説明しづらい。かっこいい言葉でいってしまえば「クリエイター」ですけど、日本語って職種を細かく分けたがるんですよ。海外だと「アート」というくくりができるんですけど、日本では「日本画」「油絵」「彫刻」とか専門ごとにカテゴライズされている。伝統工芸や職人仕事の流れなんでしょうね。
——確かに「芸術家」というと日本ではちょっと特殊な仕事というイメージになります。パッとイメージするのが岡本太郎さんとかああいう方になる。
巨匠的なイメージですよね。そういうものともちょっと違う。ハロウィンとかクリスマスとかに合わせて「こんなディスプレイはどうだろう」という感じでいろいろつくっていたり、写真も昔から好きだったので写真を撮ったり。観光地なので、写真の需要もあるんですよね。

クリスマスのミニツリー。
——でも、そうすると素材も変わるし、つくるものも変わる。毎回新しいことをやることになりますよね。大変じゃないですか。
そうですね。だから失敗もやっぱりあります。もちろん毎回失敗するわけにはいかないですから、やったことがなくてもある程度見込みを持ってやらないといけない。そういうチャレンジというか、新しいことも常にありますね。その分どうしても考える時間は長くなる。経験のない分野を開拓することも多いですから。やっぱり経験のある分野の方が効率もいいし安定はするんです。でも、新しいことができるからこそ、常に新しい引き出しをつくっていけるわけです。それが楽しいんですよね。
——何か専門をひとつに絞るというのを考えたことはないんですか?
もちろん「僕は金属作家です」みたいにいえるものを持つことに憧れもあったんです。エキスパートですね。でも、そうはならなかった。自分の性格もあって、理想と自分の資質を冷静に見たとき、本当にそれができるのかなって思ったんです。結果的にこうやっていろいろなことをやるのが合っていたんだと思います。
——逆にいえば「金属専門」とか「日本画専門」という仕事は探しやすいですが、今のモルゲンさんのような仕事ってなかなかできるところがないですよね。オールジャンルみたいな形は。
そういう環境が少ないですよね。萌木の村みたいなところだからできることで、都会ではまず同じ仕事は見つからないでしょう。どうしてももっと細分化されますから。日本中探してもなかなかないと思います。

デザイナーの小林春生さんがデザインした現在のROCKのロゴ。店舗に飾られたネーム自体はモルゲンさんがアイアンで制作しています。カラーにこだわり、光沢感のある鮮やかな「フェラーリの赤」を指定して色を付けたんだとか。
——刺激的な仕事ですね。
本当に面白いです。でも、すごくやりやすいのは、萌木の村の場合、基本的な流れや土台はちゃんと決まっているんです。自然のものを使う、自然のなかの生活のなかにあるものを使うというような線路はもうできている。だから、薪を使ったり、カボチャや牧草を使ったりするわけです。そのなかで、たとえばインスタ映えするようなものを考えようとか、アイディアを練っていく。まるっきりゼロから考えるのとは違うから、すごくやりやすいんです。それと、反応もちゃんとわかる。来られた人が楽しんでくれているか、受け入れてくれているかというのは、ここでは目に見えるので。
——反応が見えるというのはすごく大事ですよね。反応が見えないと迷ってしまう。
そうですね。今でいうといいねがどれくらい付くか、みたいなことがちゃんとわかる。人間って意味のないことをやるのが一番ツラいんですよね。だから、手応えが必要なんです。あまり狙いすぎてもダメですが。これは受け売りですが、萌木の村の商品って何かっていったらアイディアだと思うんです。ここは清里の森を舞台にいろんなアイディアを表現できるわけじゃないですか。そういう場所で、自然だけでなく、いろんなここの人たちの生活を見ていただくというか。それがここで提供される面白さだと思うんです。

昨年秋に試験的につくられたハロウィン向けのディスプレイ。本物のカボチャを使って大きなタワーにしています。今年の秋にも本格的に登場するかも?
——この場所というものをどう見せるか、ということですね。
知ってもらう、見てもらうきっかけづくりですよね。それは例えば単純に「写真に撮りたくなる」とかそういうことだと思うんです。単なる看板を立てても撮ってはもらえないけど、ここらしい面白いものなら撮ってもらえる。
カメラを持つことでより景色を心に残せる
——この場所らしさというのは重要ですよね。たとえばディズニーランドもすごく魅力的ですが、あれと同じものを清里でやっても浮いてしまう。
そうですね。ここの場合はとにかく本物でつくっちゃうというのに意味がある。電飾なんかもディズニーランドにはディズニーランドのよさがあって、カラフルで華やかなのがいいわけですが、萌木の村だともっと素朴なものが合うわけです。だから、実はここで使う電飾は今もLEDでなく一部はまだ電球だったりするんです。電気代を考えるとLEDの方がいいんですが、まだ今のLEDでは電球のような柔らかい光やゆらぎは出ない。今後LEDももっと進化していくでしょうが、今のところはまだ電球がここに合っていると思っています。
——写真の話も出ていますが、モルゲンさんは今ROCKのInstagramも担当されているんですよね。
はい。ROCKの再建とともにInstagramも立ち上げることになって、やらせていただくことになりました。もともと自分自身はSNSとは距離を置いていたんですが、やってみると面白いもんだなって思いますね。アップする写真によって反応も違うじゃないですか。そうすると、偏ってはいるんだろうけど、お客さんがどういうものを求めてここに来ているかを知る指針になる。僕は「そうでもないだろう」と思って出した写真が意外と受けたりもするんです。アカウントとしてまだまだですけど、これからどんどんそういう経験値が積み重なっていけば面白いツールになると思います。それと、僕自身もInstagramを始めてからこれまで以上にジロジロと萌木の村を見るようになりました。何かいいものはないかって探すように。

モルゲンさんの相棒のひとつであるカメラ。
——写真って面白いですよね。撮るようになると、すごくいろんなところを見るようになる。
そうなんです。山に登るときも撮っていたんですけど、帰ってきてからいろいろ話していると「よくそんなこと覚えてるね」ってみんなにいわれたりしていたんです。山に登るときってもうゼエゼエいって、しんどい思いをしながら必死で登っている。だから、みんななかなか細かいことを覚えていないんです。じゃあなんで僕が覚えているかというと、どこかにいい景色はないかと一生懸命見ているんですね。カメラを通していろんなものを心のなかに記憶できる。それはカメラのいいところだなって思います。Instagramもそういうひとつですよね。今の子たちってインスタが当たり前じゃないですか。つまり、一般の人たちも楽しんで隅々までものや景色を観察するようになっているということなんだと思います。萌木の村のいろんなものも皆さんよく見てると思うんですね。
——反面、よく見るということは魅力的なものだけでなく、よけいなものも目に付くようになりますよね。
そうそう。都会から遊びに来るお客さんって「ここにあってもいいもの」「あってはいけないもの」というのをしっかり分けていて、期待して来ている。僕らはそこをきちんと意識していないといけない。ディスプレイにしても、ニセのモミやニセのカボチャが置かれていたらガッカリするわけです。
——自然そのものではないけれど、本物を見せるということですね。

スミザーさんのガーデンなんかもそうですよね。ここに元からあった山野草を植えていると同時に、外から持ってきたものも植えて庭をつくっている。僕らはついあとから来たものは、外から持ってきたものは「外来種」だからと排除しようとしてしまうけど、スミザーさんは共存できるならよし、とする。その発想は本当に面白いです。そういうものも含めて、来る人が面白さを発見するきっかけみたいなものをつくっていけたらいいなと思っています。たとえば、雪にしても朝と昼では違うんです。朝は横から光が射すから、ダイヤモンドのようにキラキラ光って見えたりする。そういうことを知ってもらうと、同じ景色でももっと面白くなる。
——マニアの視点って面白いですよね。そこを見るんだ、というポイントを知るともっと楽しめるようになる。
そうですよね。プロもそうで、プロというのはいろんなことを知っているからプロなんです。こういうときはこうするんだ、とか。それってちょっとしたこと、なんてことないことなんですけど、知ったときの喜びはありますよね。そういうものを提示していけたらいいなと思います。