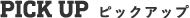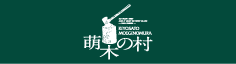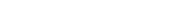「ROCKといえばビール!」というイメージを持つ人も多いと思います。もちろん店内併設の八ヶ岳ブルワリーでつくられているクラフトビールはロックの看板のひとつです。
ですが、山梨県はさまざまなお酒が集まる地域。日本酒や焼酎、ワイン、ウイスキーなど、地元でつくられるお酒がたくさんあり、ROCKでも扱っています。
そのひとつが勝沼醸造さんのワイン。ワインの醸造が盛んな山梨県でも特に多くのワイナリーが集まる甲州市勝沼町にある醸造会社です。
ROCKでも白の「アルガーノ ボシケ」や赤の「アルガーノ クラン」といった勝沼醸造さんのワインを提供しています。
ですが、こうしたワイナリーさんに直接うかがったり、話を聞く機会はやはりなかなかありません。そこで今回は、参加できるホール・キッチンスタッフで勝沼醸造さんにうかがい、ワインについて教えていただく研修を行いました。

ホール・キッチンスタッフで勝沼醸造さんへ。
※今回の研修は2020年2月に行われました。
「どうせ山梨産」と呼ばれたワインが描いた夢
そもそも勝沼醸造さんってどんなワイナリーなんでしょうか?
そのはじまりは1937年、初代社長の有賀義隣さんがスタートさせた製糸業の傍らワインの個人醸造です。家族経営で醸造を続け、現在の社長である有賀雄二さんの代になり、「世界に通用する甲州を」という目標を掲げ、「アルガブランカ」をはじめとした甲州ワインの新ブランドを立ち上げました。
2003年にはフランスの国際ワインコンテスト「ヴィナリーインターナショナル」で辛口甲州ワインとして初めて銀賞を受賞。その後も数々のコンテストで賞を受賞するワインを生み出してきました。
最近では伊勢志摩サミットで各国首脳に出されるワインに選ばれたり、2019年10月に行われた「即位礼正殿の儀」に参列する各国の元首を招いた晩餐会で提供されたりもしているんです。

今回の研修では有賀雄二社長の息子さんで、営業を担当している有賀淳さんが案内してくれました。
山梨のみならず、日本を代表するワイナリーのひとつといえる勝沼醸造さんですが、雄二社長が「世界に通用する甲州を」という目標を持ったとき、それはまだ夢物語だったそうです。
今でこそ「日本ワインブーム」といわれ、甲州ワインをはじめ国内産のワインが人気になっていますが、このブームが起こったのは2012年ごろのこと。有賀雄二さんが社長に就任した1999年ごろは、日本のワインには今ほどの市場価値は見出されていませんでした。
そんな時代に雄二社長が抱いた夢の象徴として、淳さんが紹介してくれたのがワイングラスです。
この日案内された勝沼醸造さんの蔵の2階にはワイングラスがズラリと並んでいました。これは260年以上の歴史を持つオーストリアの老舗グラスメーカー・リーデルのワイングラスです。

ズラリと並んだリーデルのグラス。
1脚2万円以上するものもあるハンドメイドシリーズ「ソムリエ」をはじめ、さまざまなグラスをつくる高級メーカーで、世界中のワイン生産者や愛好家に愛されています。このリーデルはただ技術が高いだけではありません。カベルネソーヴィニヨンを飲むためのグラス、シャルドネを飲むためのグラスといった具合に、品種や産地によって最適な形状を計算し、異なるグラスをつくっているという徹底的なワインへのこだわりを持つメーカーなんです。
社長に就任して間もないころに雄二さんが抱いたのは、このリーデルに「甲州ワイン用のグラスをつくってもらう」という夢でした。
もちろん当時の勝沼醸造は世界的には無名といっていい存在。そもそも国内でも甲州ぶどうのワインといったら「どうせ山梨のワインでしょ」と言われてしまうような状況でした。「高級ワイン」「いいワイン」といったら海外のワインで、日本固有種の甲州でつくった国産ワインなんて見向きもされていなかったのです。
しかも、2000年ごろはリーデルの日本法人もできたかできないかという時期。今のようにアウトレットモールなどで目にすることもない時代で、コンタクトの取り方すらわかりませんでした。
そこで社長が起こした行動がリーデルのハンドメイドグラスを全種類購入し、並べることでした。日本では高価なハンドメイドグラスをすべて揃えるなんて、高級ホテルでもありえない時代。リーデルも「一体誰が買ったのか」と興味を持ち、わざわざ勝沼醸造に足を運んでくれたんです。

淳さんのお話を聞くスタッフ。
社長は大胆にもそこで「甲州種用のワイングラスをつくってほしい」と伝えたのですが、当時の状況ではさすがに無茶なお願いで、やんわり断られたそうです。ですが、甲州の味を見て「それならこれを使ったらいいんじゃないか」とロワール地方のソーヴィニヨンブランを飲むためのグラスを薦められ、それから勝沼醸造の直営レストランではそのグラスを使うようになったそうです。
そんな出会いから十数年。甲州は世界でも評価されるようになり、ついに2019年4月、リーデルが「甲州」にマッチするワイングラスとして「リーデル・ヴェリタス」シリーズで「甲州」と名付けたグラスをリリースしました。
ですが、これはまだ本当の夢にたどり着いたわけではないと淳さんは話します。
「もちろんこれは我々にとって大きな第一歩です。でも、このグラスはフランスや現地だとシャンパーニュ用として販売しているもの。『甲州』に合うグラスとしてリーデルさんが選んで、『甲州用』と謳ってくれていますが、一から甲州専用につくられたものではありません。いつかリーデルを代表するハンドメイドシリーズである「ソムリエ」で甲州専用のグラスがつくられたら、そのときこそ本当の意味で『甲州』『勝沼』というワードが世界のワイン産地のひとつとして認められたときだと思っています」(淳さん)
「普通のぶどう」の真逆の考えでつくられるワイン用ぶどう
では、勝沼醸造さんではどんなワインをどんなふうにつくっているんでしょうか。
2004年に生まれ、現在の勝沼醸造を代表するブランドになっているアルガブランカは「変な甲州」がコンセプトだといいます。
「『勝沼醸造の甲州はおかしい』『甲州らしくない』っていわれるんです。でも、おかしな甲州でないと世界には通用しない。だから、父は“おかしな甲州”をつくることを自分の目標にしたんです」(淳さん)
ですが、「従来の甲州らしくない」からといって人工的にほかの地域と同じワインをつくることをめざしているわけではありません。ワインは産地の自然と人間が関わってできるもの。本来どこかのワインと比べるものではなく、その土地ごとの味を楽しむものという考えが雄二社長にはあります。ワイン自体が土地や風土とのマリアージュで生まれるものというわけです。
甲州という固有種にこだわり、この土地でしか生まれないワインをつくる。しかも、おいしいものを。
そのために新しい技術も積極的に取り入れています。たとえば氷結濃縮法。これはぶどうの果汁を低温にし、よけいな水分を凍らせることで糖分などをより凝縮させる技術です。現在の施設ではマイナス4度を維持することができる装置に果汁を入れることで、周囲だけを凍らせ、中心部はきれいに濃縮された果汁が残るようにしているそうです。
この方法では使える果汁の量は当然減ります。技術や施設だけでなく、原材料コストも上がるわけです。ですが、その分より個性の際立つワインができるのです。
また、畑も「普通のぶどう畑」とは違います。

淳さんの案内で、蔵のすぐ近くにある勝沼醸造さんの畑へ。
山梨県は古くからぶどうの一大産地ですが、基本的にはその歴史は食用ぶどうの歴史です。普通に食べるぶどうは水分が多くジューシーであることが重要。さらに、収穫量も当然多い方がいいので、1つの木にたくさんの房が付くように育てられています。
ですが、ワイン用のぶどうは考え方が逆になります。ワインづくりに重要なのはぶどうの糖度。糖度のことをワインづくりでは「ブリックス※Brix値」なんて呼ぶそうですが、ブリックス※Brix値はできあがるお酒のアルコール度数を左右します。アルコールというのは、酵母が糖分を分解する過程でできるもの。だから糖分が多ければ多いほどアルコール度数の高いお酒ができますし、低ければすぐに一定のアルコール度数以上にはなりません。ワインの場合だとぶどうのブリックス※Brix値のおよそ0.55倍が辛口のアルコール度数になるそうです。普通の甲州ぶどうだとブリックス※Brix値が15〜16度程度なので、辛口でもアルコール度数7.5%〜8%が限度となります。
ワイン用のぶどうは水分が少なく糖度が高いことが重要。だから、勝沼醸造さんの畑でもできるだけ収量を抑え、厳しい環境で育てることでブリックス※Brix値の高いぶどうをつくっています。
周辺の食用ぶどう畑などが通常1本の木から400房のぶどうを収穫しているのに対し、勝沼醸造さんのぶどう畑では200房程度だったり、さらに少ないところだと50房程度まで絞っているんです。もちろん収穫量が少なければ経営を圧迫するのは普通のぶどう農家さんと同じ。そのバランスを取りながら、よりワインに向いたぶどうをつくっています。
また、よく見ると畑ごとにその様子も違います。足もとに草が生えているような畑もあれば、草のない畑も。
草がない状態で行う栽培方法は清耕栽培と呼ばれます。土を耕して草の生えない状態で行う農業で、「畑づくり」といったらこの形をイメージする人も多いかもしれません。

こちらの畑は足もとに草が。
勝沼醸造さんの基本方針はその逆。地面にさまざまな草木が生える草生栽培と呼ばれる方法が基本です。
この方法だと当然、放っておくとどんどん草が生えてくるため、夏などは特に草刈りが大変になります。
「だけど、植物が生えているところに草が生えないっておかしくないですか? 味もやっぱり変わってきます」(淳さん)

そして、実は草が生えないようにすぐことで、ぶどう栽培もかえって手間がかかるようになるといいます。
「草が生えない状態を維持すると、今度は虫が寄って来やすくなる。そうするとかえって手間がかかるし、味も変わってしまうんです。草生栽培は、この畑にいろんな草が生える生態系をつくっていて、そこでうまくまわるようになる。」(淳さん)
勝沼醸造さんの畑はいろんな農家さんから譲り受けているため、なかには長年清耕栽培を行っていた畑もあります。そうしたところはすぐに土壌の状態も変わらないので、徐々に移行しているわけです。
ちなみに、淳さんは3人兄弟の次男で、お兄さんは醸造を、そして弟さんは栽培を担当しています。兄の裕剛さんはフランスのブルゴーニュに修行をしていたのですが、帰国してしばらくたったころ雄二社長が植えたカベルネソーヴィニヨンとシャルドネを全部抜いてしまったそうです。「甲州で一番になるんだろう? だったら甲州を植えなきゃ」といったんだとか。社長も大胆ですが、息子さんたちも大胆で強い意思を持っているんですね。
産地が違うだけでも別物になるワインという飲み物
畑を見たあとはテイスティングへ。勝沼醸造さんの看板ともいえる「アルガブランカ クラレーザ」や即位の儀の晩餐会でも提供された「アルガブランカ イセハラ」をはじめ、「アルガーノ ボシケ」「アルガブランカ ピッパ」といったワインを実際に試させてもらいました。

実際にいろんなワインを試させてもらいました。
ワイン自体の味ももちろんですが、ここでスタッフが驚いたのはグラスによる味の違い。同じワインでもグラスが違うだけで香りや味の感じ方がまったく違うものになるんです。
リーデルのグラスの話で説明は受けていたものの、実際に自分で体験すると「こんなに違うのか!」と驚くスタッフが多かったです。
そしてもうひとつ驚いたのは、クラレーザとボシケの飲み比べ。それぞれ違う個性を持った別のワインなんですが、実はこのふたつ、つくり方も使っているぶどうの品種もまったく同じなんだそうです。
では何が違うのかというと、ぶどうの産地。クラレーザは勝沼が中心なんですが、ボシケは同じ山梨県の笛吹市の砂地の土地でつくられたぶどうを使っているんです。同じ品種でも砂地の土壌だとぶどうが育つのにより力が必要になるため、力強い味になります。だから、できあがるワインも別物に。産地が違うだけでこんなに個性が変わるというのは、かなり驚きでした。

こうした産地の違いは、プロ中のプロとなると味で判別してしまうこともあるそうです。淳さんも驚いたのは「イセハラ」をロンドンに持っていったときのこと。試飲した人が「これは砂地だね」といったそうです。まさに「イセハラ」に使っているぶどうは、砂地の土地で育てられたもの。もちろんそんなことは知らないはずの外国の方が、ワインを飲んだだけで産地の土壌まで当てたのには、淳さんもびっくりしていました。
ちなみに「ボシケ」というのはポルトガル語で「林」を意味する言葉。勝沼醸造ではこのほかに「風」を意味する「ヴェント」、「火」を意味する「フォーゴ」、「山」を意味する「モンテ」といったワインも出しています。
これは勝沼醸造さんの家に代々伝わってきた家紋が戦国大名として知られる武田家の「武田菱」であることが由来。武田信玄が軍旗に使った「風林火山」をワインの名前に使っているというわけです。受け継がれてきたものを、こういう形でつないでいるんですね。
ボシケ」に限らず、勝沼醸造さんのワインは多くにポルトガル語が使われています。「クラレーザ」は「クリア」、「ブリリャンテ」は「ブリリアント」といった意味です。
新ブランドの立ち上げ当初、味には自信があったけれど「甲州」「勝沼」といった言葉はブランド力がなく、むしろ「どうせ山梨・国産」といわれてしまう原因になっていました。だから、あえて「甲州」といった言葉を使わずに名前を付けることにしたんです。
ポルトガル語が選ばれたのは、「アルガ」という名前がポルトガル語っぽいといわれたことがきっかけ。ポルトガル語ではワイナリーを「アデガ」と呼ぶそうで、たまたま「アルガ」と似た言葉だったんです。そこで、「ならいっそ全部ポルトガル語で」と、さまざまなワインにポルトガル語の名前が付けることにしたんだとか。

さらに勝沼醸造の味の秘訣の話も。淳さんは勝沼醸造のワインで大事にしているのは「中毒性」だといいます。
「中毒性というのはつまり、また飲みたくなるということ。気付いたらこんなに飲んでいた、とかそういうことが大事だと思っています。じゃあ、どういうものに中毒性があるかというと、人間ってちょっとクセのあるものが好きなんです。つい嗅いでしまう匂いとかって、クセがあるでしょう? もちろんそれが強すぎてもダメなんですが、いわば『見えない欠点』みたいなものが中毒性を生むクセだと思っています」(淳さん)
勝沼醸造さんのワインでいえば、たとえばフェノール感がそれだといいます。フェノール感というのはポリフェノールの生む感覚。タンニンなどのわずかな苦みの感覚が、白ワインにも残るように、少しだけクセのある味に仕上げているそうです。

メモも取りながらテイスティング。
このほか、テイスティング中はスタッフからも「このワインの香りはなんて説明すればいい?」「オススメを聞かれたときはどう答えればいい?」なんて質問も盛んに飛んでいました。
そして、テイスティングのあとは蔵をあとにして勝沼醸造さんの直営のレストラン「風」へ。名物のローストビーフをはじめ、コースとともに食事とワインを楽しませていただきました。

レストラン「風」。勝沼醸造さんから徒歩でも10分前後です。

名物は特選和牛ローストビーフ。目の前で切ってもらいました。ワインといっしょに食べるとまた格別!
レストランはワインの楽しみ方をどう広げるか?
今回の研修に参加したスタッフは、普段からワインを飲む人、ある程度詳しい人もいますが、普段はあまり飲まない人、お酒自体が飲めない人もいました。運転の関係でテイスティングせず、香りだけ楽しんだという人もいます。
ですが、こうして生産者さんの思いやこだわりに触れることで、飲めないスタッフでもワインについて聞かれたとき、伝えられることはかなり多くなります。グラスによって味が変わることや、ぶどうの産地の違いだけで別のワインになることを伝えれば、飲む人の楽しみ方も膨らむでしょう。
「面白かった」「勉強になった」という感想はもちろんですが、「この研修のあと、スタッフの接客がどんなふうに変わっていくかも楽しみ」なんて声も。同じ知識や体験でも、スタッフによって伝え方、活かし方が変わってくるはず。スタッフの個性を大事にするROCKですが、こうした経験や勉強によって個性の幅がさらに広がっていくといいなと感じる研修でした。